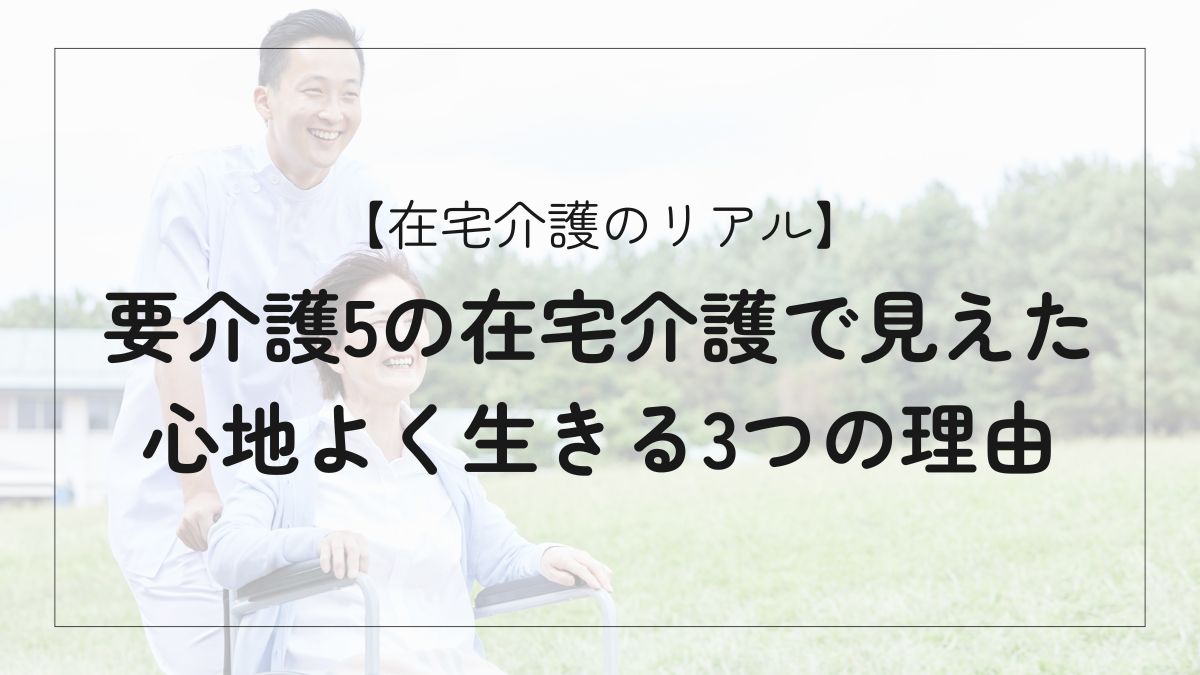要介護5
多くの人が”もう在宅での暮らしは難しい”と感じるかもしれません。
私自身も父の介護に直面したとき、
「もう無理かもしれない」と心が折れそうになったのを今でも覚えています。
想像以上に大変な現実に、何度も立ち止まりそうになりました。
それでも、父も私たちも、この家で自分らしく生きたいという思いだけは諦めたくなかったのです。
完璧を目指すのではなく、周囲の支えや小さな工夫をひとつずつ積み重ねていくことで、要介護5という現実の中でも “心の豊かさを失わない暮らし” を見つけることができました。
この記事では私が在宅介護の中で実感した心地よく暮らすためのヒントを、リアルな体験を交えながらお伝えします。
要介護5となった日|私が感じた「無理かもしれない」という葛藤
24時間見守るという現実
父が要介護5と認定されたとき、最初に頭に浮かんだのは”今までの生活はできない”という現実でした。
食事や排泄、入浴など、生活のほぼすべてにサポートが必要です。
正直、その事実に直面した瞬間は頭が真っ白になり、介護経験のまったくない私にとって、その重さは想像をはるかに超えるものでした。
幸いなことに、父は脳梗塞による要介護で、認知機能には大きな問題はありませんでした。
「在宅で父の尊厳を守りながら、できる限りのことをしたい」という思いが強かったため、私たちは在宅介護を選びました。
もし認知症の症状が重ければ、施設という選択肢を真剣に考えていたかもしれません。
介護者としての恐怖とプレッシャー
在宅介護を始める前、施設でオムツ交換や車椅子への移乗方法を教わりました。
初めての体験に戸惑いながら
「本当に私にできるんだろうか」
「途中で私が倒れてしまったらどうしよう」
と恐怖に押しつぶされそうになったことを覚えています。
それは単なる身体的な負担の懸念ではなく「介護者という役割を完璧に果たさなければ」という、自分自身への強いプレッシャーでもありました。
家族にとっての大きな決断
在宅介護か、施設入所か。
私たちは家族で何度も話し合いました。
お互いに不安な気持ちを正直にぶつけ合い、
最終的には「まずはやれるところまでやってみよう」という結論に至ります。
この決断は、私たち家族にとって大きなターニングポイントでした。
そしてこの一歩があったからこそ、
介護生活の中で少しずつ 「わたしらしい」 道を見つけていくことができたのです。
介護生活を変えた私たちを支えた3つのヒント
在宅介護を始めた当初は、不安や焦りから「完璧にやらなければ」と気負ってしまいがちです。
しかし、そんな日々を変えてくれたのは、介護を “孤独な作業”から“みんなの関わり” に変えるための3つのヒントでした。
1.介護サービスをフル活用する勇気
「人に任せるのは申し訳ない」
「金銭もかかるしどうしようか」
そう感じる介護者は少なくありません。
私も初めはそうでした。
親の年金で家の生活や介護代できるのかと必死にやりくりしていました。
でも介護は一人で抱え込むものではありません。
介護サービスは、介護者の心と体を守るためにある大切なセーフティネットです。
・訪問介護・訪問看護
自宅に来てもらうことで専門的なケアを受けながら負担を軽減できる。
・デイサービス
日中の利用で介護者が自分の時間を持てる。心に余裕が生まれる。
・レスパイトケア(短期入所)
短期間預けることで、まとまった休息を取れる。
実際に初めてデイサービスをお願いした日。
朝9時に迎えがきてそのまま出発。
そのまま何もせず(何もできず)久しぶりに昼寝をしました。
その時、「ああ、休んでもいいんだ」と心から実感できたのです。
介護を続ける上でとても大切な気づきでした。
2.ひとりで抱え込まない家族や地域の協力
介護を自分だけの問題にしないことも、心地よく続けるための大切なポイントです。
家族はもちろん、協力してくれる近所の人や友人にも「少し手伝ってほしい」と声をかける勇気を持ちましょう。
たとえば、スーパーに行ったついでに飲み物を買ってきてもらう、庭の手入れをお願いする。
そんな些細なことでも構いません。
小さな助け合いが積み重なることで、介護は“みんなで支え合うこと”へと変わっていきます。
地域との「つながり」を再構築し、孤立を防ぐという意味で、非常にエシカルな選択だと感じています。
3.暮らしを整える小さな工夫(道具と環境づくり)
介護は体への負担がとても大きいもの。
私も父の身体を起こすだけでも一苦労しています。
だからこそ便利な道具や環境を積極的に取り入れることも、在宅介護を無理なく続けるための賢い方法です。
介護保険制度を利用すれば、介護ベッドや車椅子をレンタルできます。
私の場合、車いすと介護用ベッドをレンタルしています。
マンションに住んでいるため段差の問題も出てきますがスロープもレンタルできるため高さを確認しておくのも良いです。
手すりやスロープの設置も、被介護者だけでなく介護者自身の身体的な負担を大きく減らしてくれます。
手すりの設置は金銭が大きく掛かってしまいますが、助成金などもあるため住んでいる自治体に確認してみるのも良いでしょう。
「ちょっと便利な道具」が、日々の介護をずっと楽にしてくれるのです。
完璧な環境を目指す必要はありません。
できる範囲で少しずつ暮らしをアップデートしていくことが、心にも体にも優しい介護の形だと思います。
私たちが大切にした心のウェルビーイング
介護は身体的なケアだけでなく、介護する側とされる側、両方の心の健康を守ることが欠かせません。
私たちは在宅介護の中で、自分たちなりのウェルビーイングを育むヒントを少しずつ見つけていきました。
・本人の意思を尊重するエシカルケア
・介護者のセルフケアを最優先にする勇気
・完璧じゃなくていいと受け入れたときに生まれる心地よさ
1.尊厳を守る関わり方:本人の意思を尊重するエシカルケア
要介護5という状態になっても、「自分で何かを決めたい」という気持ちは決して消えません。
たとえば、その日の食事のメインディッシュ。
そんな小さなことでも、父の意思を尊重することを大切にしました。
選択肢をいくつか示し「どちらがいい?」と尋ねることで、父は自分らしい人生を歩んでいると実感できていたと思います。
ちなみに”何でもいい”という言葉は許しません(笑)
相手の尊厳を守る、エシカルな関わり方であり、介護者の負担を減らしつつ、被介護者の自己決定を尊重できる方法でもあります。
2.介護者のセルフケアを最優先にする勇気
「自分のために時間を使うなんて、わがままでは?」
在宅介護を始めた頃、私は常にそんな罪悪感を抱えていたのかもしれません。
けれど介護生活が長くなるにつれ、正直疲れました。
「自分が元気でいることこそ、介護を続けるために不可欠」だと気づいたのです。
そうしないと介護もできませんから。
好きなことをする時間や友人と話す時間、ただぼーっとする時間。
そうしたセルフケアを意識的に取ることで心にゆとりが生まれ、結果として父により優しく接することができました。
自分のウェルビーイングを大切にすることは、わがままではなく、相手を思いやるための「愛のかたち」なのだと思います。
3.「完璧じゃなくていい」と受け入れたときに生まれる心地よさ
介護は毎日が計画通りに進むわけではありません。
「今日は疲れて全部はできなかった」
「こんなことでイライラしてしまった」
そんな日もあります。
でも「まあ、そんな日もあるよね」と、完璧じゃない自分を受け入れられるようになったとき、不思議と気持ちが軽くなりました。
介護のゴールは完璧なケアをすることではなく、父と私たちの 心地よい暮らしを続けること。
そう考えられるようになってから、介護は義務ではなく自然で心豊かな時間へと変わっていったのです。
介護生活で見つけた小さな希望
介護生活は、できないことが増えていくように感じ、つい悲観的になってしまうことがあります。
恐らく大半が悲観的になるでしょう。
けれど私たちは、その日々の中で「小さな喜び」や「希望」を見つける視点を学びました。
それは完璧ではないけれど、たしかに心地よい暮らしを築くための大切なヒントだったのです。
1.「できないこと」より「できること」に目を向ける
父の身体が少しずつ不自由になるにつれて、以前できていたことができなくなる現実に直面しました。
しかし私たちは、「失われたもの」を数えるのをやめ、「今できること」を見つけること に意識を切り替えました。
「昔の思い出話で盛り上がった」
「笑顔が見られた」
そんな一瞬一瞬が私たちに大きな希望を与えてくれました。
小さな「できた」を大切にすることで、日々の暮らしに温かさを取り戻すことができたのです。
2.環境や制度を「わたしらしく」味方につける
介護の負担を減らすには一人で頑張るのではなく、社会の仕組みを利用することも大切です。
私は介護保険制度や地域の福祉サービスを徹底的に調べ、私たちに合ったサポートを組み合わせることで、心にゆとりが生まれました。
自治体によって利用できるサービスや申請方法は異なるため、まずは地域の窓口に相談してみるのがおすすめです。
こうした制度は、介護を続けるための強い味方であり、自立したエシカルな暮らし を支える基盤でもあります。
3.暮らしの中に小さな楽しみを残す
忙しい介護生活の中でも、小さな楽しみを残すことは心の栄養になります。
- 父の好きなテレビ番組を一緒に観る
- 暖かい日には、車椅子で近所を散歩する
こうした何気ない瞬間が介護生活を彩り、私たちに「この暮らしも悪くない」と思わせてくれました。
自分と相手、どちらのウェルビーイングも大切にすることが、人生の豊かさにつながる。
介護を通じて、そのことを深く実感しています。
まとめ|わたしらしい介護の形を見つけていく
在宅介護には「大変なもの」という強いイメージがあります。
実際、そのイメージは決して間違いではありません。
正直なところ
楽な道ではないし誰にでも気軽におすすめできるものではありません
それでも、私たち家族は介護を通して「心地よさ」や「自分らしさ」を見つけることができました。
それは、「完璧じゃなくてもいい」「ひとりで抱え込まない」 という、小さな諦めと工夫を積み重ねてきたからに他なりません。
介護者のセルフケアは、わがままではありません。
自分を大切にするという愛のかたちだということ
この愛があるからこそ、父の尊厳を守り、在宅での暮らしを諦めないという選択ができたのだと感じています。
介護は誰にとっても突然始まる、終わりの見えない長い旅のようなものです。
だからこそ、自分と大切な人が心豊かに歩んでいける道を、少しずつ探していくことが大切です。
あなたにとっての「わたしらしい介護」とは、どんな形でしょうか?
この記事が介護に悩む誰かの心に、温かい光を灯すきっかけになれば幸いです。