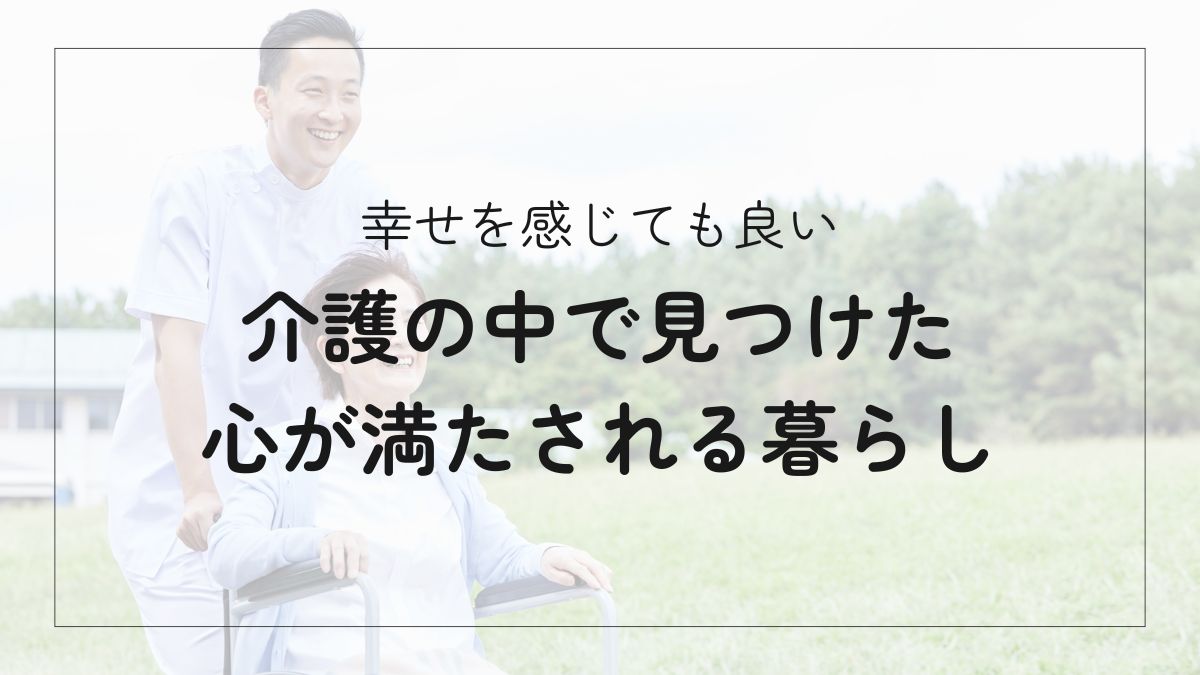介護をしていると
「自分が幸せを感じるのは、わがままなのではないか?」
と、、罪悪感に襲われることがあります(ありました)
毎日必死で向き合っているのに、
心のどこかで「もっと頑張らなければ」と自分を追い込んでしまう。
そんな矛盾した気持ちを抱えている方もいるのではないでしょうか。
しかし”介護者が幸せであること”は、決してわがままではありません。
私自身、父の介護で辛さを感じる中でも、心が満たされる瞬間があったからこそ、前に進む力を失わずにいられました。

自分らしい幸せを見つけ、それを大切にすること
結果的に心地よい介護を続けるための揺るぎない土台になるのだと気づいたのです。
この記事では、介護する人が日々の暮らしの中でウェルビーイングを育み、心と体を守るための具体的なヒントをご紹介します。
完璧を目指すのではなく「わたしらしく」 心を満たしながら歩んでいくための道しるべになれば幸いです。
介護者の幸せは「わがまま」ではない理由
介護生活では”自分の幸せは後回し”と考えてしまいがちです。
介護者が心身ともに満たされていることは、わがままではなく、むしろ介護の質を高め、心地よい関係を築くために欠かせない要素だと私は思います。
介護者のウェルビーイングが介護の質を高める
介護する人の心に余裕が生まれると、そのやさしさは自然と被介護者に伝わります。
笑顔で向き合える時間が増えたり、小さな変化に気づけたり。
これは在宅介護だけでなく、施設でのケアにも共通することです。
逆に介護者が強いストレスを抱えていると、その感情は知らず知らずのうちに介護される側にも影響してしまいます。
犠牲の介護は誰のためにもならない
「自分を犠牲にしてでも完璧に介護しなければ」とがむしゃらに頑張っていた頃、私は心も体も疲れ果てていました。
そんな状態では、心からのやさしさを注ぐことができず、介護が義務感へと変わり、やがて行き詰まってしまったのです。
しかし、自分の時間を少しずつ持つようになってから、不思議と介護にも穏やかな気持ちで向き合えるようになりました。

心にゆとりが生まれることで、相手へのやさしさが育まれるのだと実感しています。
幸せは介護を続けるためのエネルギー
介護者が幸せを感じることは、介護を長く続けるための大切なエネルギーです。
自分が元気で満たされていることは、被介護者にとって一番の安心材料にもなります。
「介護だから幸せを感じてはいけない」
という考えを手放し自分も幸せでいいと心から思えること。
これこそが、長い介護生活を支えるものだと私は思います。
今日からできる!心が軽くなる3つのセルフケア
介護は心身ともに消耗します。
だからこそ、日々の生活に意識的に 「自分のための時間」 を設けることが、心の健康を保つために欠かせません。
ここでは私が実際に試して効果を感じた、3つのセルフケアのヒントをご紹介します。
- 小さな休憩時間を意識的に見つける
- 気持ちを話せる相手や場を持つ
- 感情をため込まない工夫をする
1.小さな休憩時間を意識的に見つける
「休む時間なんてない」と感じるかもしれません。
けれど、たった5分でも十分です。
例えば私がよく行うのは
- 一杯のコーヒーで心を落ち着かせる
⇒父の朝食を終えた後にコーヒーを飲む時間は、1日を穏やかに始める習慣になっていました。 - 窓から外の景色を眺める
⇒短い時間でも介護から意識を離すことで、気持ちをリセットできます。 - 近所を散歩する
⇒外の空気を吸えば、気分転換になり心身の緊張が和らぎます。
完璧な休憩時間を作る必要はありません。
暮らしの中にある”小さな隙間”を意識的に使うことが大切です。
2.気持ちを話せる相手や場を持つ
介護の孤独は心をじわじわと蝕みます。
感情を一人で抱え込まず、誰かに話すことが心を軽くする第一歩です。
- 友人や家族
⇒信頼できる人に素直な気持ちを打ち明けるだけで、安心につながります。 - 地域の支援者
⇒ケアマネジャーやヘルパーに気持ちを共有するのも一つの方法です。思わぬ解決策が見つかることもあります。 - ケアラーズカフェ
⇒同じ立場の人と出会える場。私だけじゃないと思えるだけで救われます。
私は利用したことありませんが、各都道府県にケアラーズカフェ(認知症カフェ)というものがあります。
“認知症カフェ×お住いの地域”で検索していただくと見つかるはずです。
私の場合、横浜市に住んでいるため、横浜市の情報サイトを参考までに記載しておきます。
>>横浜市役所公式集いの場(認知症カフェなど)
3.感情をため込まない工夫をする
これが一番難しいかもしれません。
怒りや悲しみ不安を抱え込むと、心身の不調につながります。
外に出す習慣を持ちましょう。
- 日記に書き出す
⇒出来事や感情をそのまま書くだけで気持ちが整理されます。 - 信頼できる人に話す
⇒感情を客観的に見直すきっかけになります。 - 泣く
⇒我慢せず涙を流すことも大切。
涙にはストレス軽減効果があるとも言われています。
これらのセルフケアは自分を大切にすることそのもの。
そしてそれこそが介護を長く続けていくために欠かせない力になるのです。
質の良い睡眠と栄養で介護に負けない体をつくる
介護は心だけでなく体にも大きな負担をかけます。
自分の体を後回しにしていると、やがて心身のバランスを崩し、介護を続けること自体が難しくなってしまいます。
介護者が自身のウェルビーイングを保つために欠かせない身体的なケアについてお伝えします。
- 眠ることを最優先事項にする
- 簡単でも栄養を意識した食事をとる
- ストレッチや散歩などの軽い運動を習慣にする
眠ることを最優先事項にする
睡眠不足は心身の不調を招く最大の敵です。
実は常に介護をしなきゃという気持ちで睡眠を削っていた時期、私の母も心身に不調をきたしました。
その経験から「休むことを優先する」と決めることの大切さを痛感しました。
介護はいわば長距離走のようなもの。
被介護者にとっても、介護者が元気でいることが一番の安心材料です。
夜、被介護者が眠った後は、無理に家事をせず、できる限り一緒に体を休めることを意識するのがおすすめです。
簡単でも栄養を意識した食事をとる
忙しい介護生活では、つい食事を疎かにしがちです。
しかし、栄養バランスの取れた食事は、介護者にとって何より大切なエネルギー源になります。
具だくさんのスープを作ったり、時には冷凍食品や惣菜を活用するのも良いでしょう。
とにかく介護者の負担を少しでも減らすことが大切です。
「簡単でもいい」と自分に許可を出すことで、
準備のハードルが下がり、無理なく続けられます。
ストレッチや散歩などの軽い運動を習慣にする
大きな運動でなくても構いません。
体を少し動かすだけで、心身のリフレッシュ効果があります。
- 朝の5分ストレッチ
⇒起床後や介護の合間に体を伸ばすと、筋肉の緊張がほぐれ、気分もすっきりするそうです。 - 近所の散歩
⇒10分だけでも外を歩けば、日光を浴びて心身の調子を整えることができます。
もし外出するのが難しいというのであれば、隣でラジオ体操するのはどうでしょうか。
私の場合、朝の朝食がひと段落してから父の隣でストレッチを入念にこなしています。
介護という長旅を健康に歩み続けるために、自分の体をいたわる時間を意識的に確保することが大切です。
介護生活で見つける「わたしらしい」幸せの育て方
介護生活は自分の時間や楽しみを諦めなければならないと思いがちです。
しかし、そんな中でも日々の暮らしに 「自分らしさ」 を残すことが、心のウェルビーイングを育む上でとても大切です。
- 自分だけの楽しみを手放さない
- 小さな達成感を数える習慣
- ありがとうを素直に受け取る
自分だけの楽しみを手放さない
読書や映画、ドラマ、音楽。
どんなに小さな趣味でも、あなた自身を支える大切な時間です。
お恥ずかしながら私自身、在宅介護を始めてからアニメを観る時間が増えました(笑)
短時間で完結する作品も多いので隙間時間でも楽しめますし、非日常の世界に触れることで気持ちをリセットできました。
大切なのは完璧な時間を確保しようと気負わないことです。
たとえ10分でも、好きなことに没頭できる時間を持つことが、心の豊かさにつながります。
小さな達成感を数える習慣
介護生活は大きな成果が見えづらいものです。
むしろひどくなってしまうことの方が多いかもしれません。
「できていないこと」にばかり目が向き、自己肯定感が下がってしまうこともあります。
そんな時は”小さな達成感”を意識的に見つけてみましょう。
- 薬を飲ませるのを忘れなかった
- 一緒に好きなテレビ番組を観て笑い合えた
- 部屋の換気をしっかりできた
どんなに小さなことでも「これができた」と自分を認めてあげること。
その積み重ねが心の栄養となり、前向きに介護を続ける力になります。
ありがとうを素直に受け取る
介護をしていると、周囲からの”ありがとう”をつい遠慮してしまうことがあります。
「当たり前のことをしているだけですからね」
でも、その言葉を素直に受け取ってみてください。
被介護者や家族、友人、地域の支援者からの「ありがとう」は、努力が報われる瞬間であり心を満たす大切なきっかけにもなります。
あなたが頑張っていることを周囲はちゃんと見ていますし、その感謝を遠慮なく受け取ることが、自分自身を認めることにつながり、介護を続ける自信となるはずです。

という私も少し前まで”ありがとう”を遠慮していた時期もありましたが、今は言われたいし皆さんに伝えたいですね。
私が介護で学んだ幸せを感じる瞬間
介護生活を通して私は幸せは探すものではなく、日々の暮らしの中で育まれるものだと学びました。
ここでは私が実際に経験した、心が満たされる3つの瞬間をご紹介します。
- 介護の合間に見つけた小さな喜び
- 人に頼ることで得られた安心感
- 完璧じゃなくていいと受け入れたときの解放感
1.介護の合間に見つけた小さな喜び
介護の日々はルーティンワークの連続です。
けれど、その中でもふと心が温かくなる瞬間が訪れます。
- 散歩中に見つけた道端の小さな花
- 好きな音楽を聴きながら味わうコーヒーの一杯
- 父の顔に浮かんだ無邪気な笑顔
昔の私なら道端の花に興味を示しませんでしたが(笑)
こうした何気ない一瞬が、私の心を満たし、また明日も頑張ろうという気持ちにしてくれました。
2.人に頼ることで得られた安心感
「自分で頑張らなければ」と思っていた頃は、常に孤独と隣り合わせでした。
しかし、訪問介護や家族に頼るようになってからは、「ひとりで抱え込まなくていいんだ」という安心感に包まれるようになったのです。
自分の時間が少しできただけで、心にゆとりが生まれました。
この”時間”と”ゆとり”こそが、私にとっての大きな幸せでした。
誰かに頼ることは、決して弱さではありません。
むしろ、介護を長く続けるための賢明でエシカルな選択だと感じています。
3.完璧じゃなくていいと受け入れたときの解放感
このブログのテーマでもある”完璧じゃなくていい”
介護生活では思ったように進まないことが多くあります。
「今日は予定通りにできなかった」
「もっと優しくできたのに」
と、自分を責めてしまう日もありストレスを感じたりしてました。
でも、「それでもいい」と不完全な自分を受け入れられた瞬間、心がすっと軽くなったのです。
介護のゴールは完璧なケアをすることではありません
自分と大切な人が、心豊かに暮らし続けること。
そのことに気づいてから、毎日が少しずつ心地よいものに変わっていきました。

今まさに介護に悩んでいる方にとって、小さな光となり、前に進むきっかけになれば嬉しいです。
まとめ|介護者の幸せは介護を続ける力になる
介護者が幸せであることは、決してわがままではありません。
それは自分自身を大切にするという愛のかたちであり、長く続く介護という旅を歩んでいくために欠かせない力です。
あなたが心身ともに満たされていることは、大切な人の安心にもつながり、結果として介護の質を高めてくれます。
幸せは、宝くじに高額当選するのような特別な出来事ではなく、日々の小さな工夫や、ささやかな瞬間の積み重ねから育まれるものなのです。
このブログ記事があなたが抱える罪悪感を少しでも軽くし、心にゆとりをもたらすきっかけになれば幸いです。
今日からできる “自分を幸せにする工夫” 、それは何でしょうか?
あなたの心の声に、そっと耳を傾けてみてください。