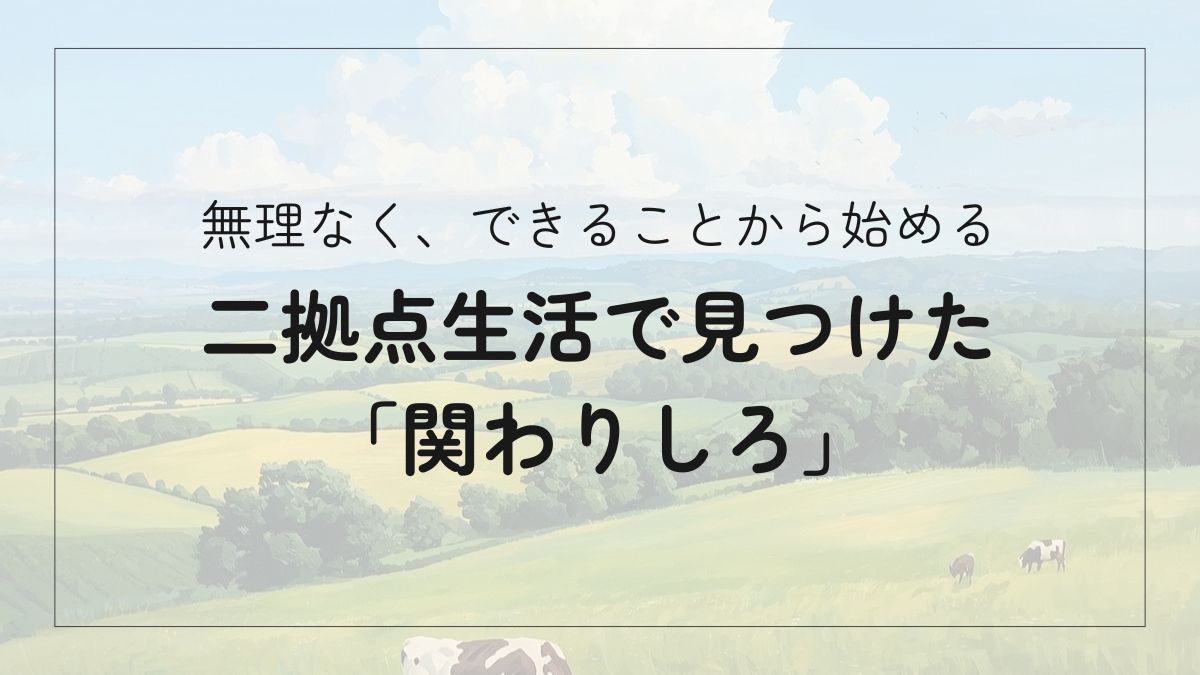「地域の役に立ちたい。でも、何ができるんだろうか?」
二拠点生活を始めたばかりの頃は、傍から見れば中途半端であり私はそんなモヤモヤを抱えていました。
人口減少や空き家、後継者不足…。
どれも大きな問題に思えて「自分には何もできない」と無力感を覚えることもありました。
そんなとき、地域おこし協力隊として活動する中で出会ったのが、”関わりしろ”という考え方です。
「その土地とのちょっとした接点や、自分が関わることのできる余地やゆとり」のこと。
特別なスキルや大きな成果は必要ありません。
完璧な貢献を目指すのではなく、
「わたしらしく」できる小さな関わりを一つずつ重ねていけばいい。
この考え方に出会ってから、地域での暮らしは楽しくなり、協力隊の活動も、私自身の心も満たされるようになりました。
この記事では、その”関わりしろ”をどう見つけ、どう関わっていけばいいのか。
私の実体験を交えてお伝えします。
関わりしろ?地域とのつながりの第一歩
地域の役に立つと聞くと、何か大きな行動や成果を出さなければならないと思うかもしれません。
実際に私が地域おこし協力隊として活動していたとき、
周りの協力隊員はとてもアグレッシブに動き、目に見える成果を上げていました。
正直なところ、
私は焦りを感じていた時期もありました。
でも私が考える 「関わりしろ」 は、もっとシンプルなものです。
それは「ここにいてもいい」と感じられる場所や「ちょっと気になるから声をかけてみよう」と思える小さな余白のことです。
完璧な貢献を目指す必要はありません。
ただそこに身を置いてみる。
それだけで、地域との関わりの種は自然に芽吹いていきます。
「関わりしろ」が生まれる場所と行動例
日常の中には思いがけず「関わりしろ」が隠れています。
たとえばこんな場所から始めてみませんか。
- 直売所
野菜や果物を買うときに「この野菜、どこの畑で採れたんですか?」と声をかけてみる。
会話が弾めば、思わぬ地域情報を聞けることも。 - 図書館
地域イベントのチラシを手に取ったり、地元の歴史資料を読んでみる。
土地の背景を知ることで愛着が湧いてきます。 - 公民館・掲示板
イベントに申し込む勇気がなくても大丈夫。
掲示板を眺めて「どんな活動があるのか」を知るだけでも、十分な一歩になります。
私は地域おこし協力隊として活動を始めた頃は、知り合いが誰一人もいませんでした。
だからこそ、まずは「話す」「見る」「そこにいる」ことを意識しました。
その積み重ねが、少しずつ地域の中に自分の居場所をつくっていったのです。

最初の一歩は”ちょっと気になる”を行動に移すこと。それだけで十分です。
私が出会った“地域課題”と小さなアクションたち
地域との関わりを深めていくと、その土地が抱える課題も自然と見えてきます。
私が地域おこし協力隊で耳にしたのは、こんな声でした。
- 若い人が参加しない
- 空き家が増えている
- 後継者がいない
- 何やっても無理
- そもそも地域おこし協力隊なんて必要ない(笑)
最初は大きすぎて、自分には関われない…と正直思いました。
中には「協力隊なんて必要ない」と厳しい声をかけられることもありました。
でも、無理に課題を解決しようと考えなくてもいいのです。
大切なのはわたしにできる小さなことを一つずつ見つけていくことではないでしょうか。
大きな成果ではなくても、日々の暮らしの中でできるアクションは、実はたくさんあるのだと気づきました。
私が実践した小さなアクション
- 直売所の野菜をSNSで紹介
- 農作業を手伝う
直売所の野菜をSNSで紹介する
近所の直売所で珍しい野菜を見つけ、許可を取り写真を撮ってSNSにアップしました。
すると「こんな地元の野菜があるんだ!」と都会の友人が興味を持ってくれたり、
地元の人から「その野菜はね…」と声をかけてもらえたり。
小さな投稿でしたが、地域の魅力を外に発信するきっかけになりました。
農作業を手伝う
初めて田植えを手伝った日のことは忘れられません。
泥だらけになりながら、12〜15cmほどの小さな苗を植えていく作業は想像以上に大変でした。(田んぼの隅っこあたりでも)
作業が終わったら、
お昼ご飯に誘われ農家さんの家でカレーをごちそうになりました。
都会では決して得られない
「土や水に触れる感覚」や「人の温かさ」を感じられ、心が不思議と軽くなったのです。
上記以外にも様々なことを行いましたが、地域課題を解決しようと気負う必要はありません。
まずは 「何ができるかな?」 と、自分の暮らしの延長線で関わってみること。
これは地域おこし協力隊の活動においても同じです。
最初から前回で行くと疲れてしまいますしね。
その小さなアクションの積み重ねが、やがて地域の未来を支える力になると実感しました。

大きな課題もひとつの小さな行動から始まります。“できること”を重ねることで地域とのつながりは確かに深まっていくはずです。
都市と地方|どちらの視点もあるからこそできること
二拠点生活の最大の強みは、「よそ者」と「住民」両方の視点を持てることです。
これは本当に大きな財産だと感じています。
地方にいると地元の人にとっては当たり前すぎて気づかれていない魅力に、よそ者だからこそ出会えることがあります。
たとえば、私が暮らしていた酒田では
- 海風を受けて育つ野菜の味わい
- 季節ごとに表情を変える地元の祭りの深み
- 集落に息づく伝統工芸
- ネットでも紹介されていない隠れたスポット
- 春の山菜採り、夏に響くひぐらしの声
挙げ出したらキリがありません。
そんな日常の一つ一つに、確かな美しさや豊かさが息づいています。
こうした魅力を伝え手として外へ発信するだけでも、立派な地域貢献だと思います。
難しいことをする必要はありません。
- スマートフォンで写真を撮ってSNSに投稿する
- 都会の友人にその土地の魅力を話して聞かせる
それだけで地域と外の世界をつなぐ小さな架け橋になれます。
二つの拠点を行き来する私たちだからこそ、地域に眠る価値を「気づき」として拾い上げ、外へ伝える役割を果たせるのです。

当たり前を見つけて“まだ知られていない魅力”として伝える。
それも立派な地域貢献だと思います。
「貢献」って何だろう?“わたしらしい”関わりのかたち
地域への「貢献」と聞くと、
「長く住み続けなければいけない」
「ボランティアに多くの時間を費やさなければいけない」
といったイメージを持つ方もいるかもしれません。
でも、それは一つの思い込みかもしれません。
もちろん定住は素晴らしいことですが、二拠点生活だからこそできる関わり方もたくさんあるのです。
大切なのは無理せず続けられる範囲で
- 写真が好きなら
地域の美しい風景や日常の何気ない瞬間を写真に残しSNSで発信する。 - 文章が得意なら
地元のイベントやお店の魅力をブログや記事にまとめ、多くの人に届ける。 - 体を動かすのが好きなら
農作業を手伝ったり、地域イベントのスタッフとして参加してみる。
どんなに小さなことでも、この地域と関わりたいという気持ちは、地域にとって大きな力になります。
週末だけでも、数ヶ月に一度だけでも大丈夫。
その関わってみたいという気持ちこそが、地域とあなた自身の関係を豊かにし、エシカルな一歩へとつながっていくのです。

貢献って特別なことじゃなくてもいいんです。あなたの得意や好きなことを地域にちょっと分け合うだけで、それは立派な関わりになりますよ。
まとめ|「関わる」ことで見えてくる地域も自分も
地域との関わり方に“正解”はありません。
だからこそ完璧な貢献を目指さなくても大丈夫。
大切なのは「心があるかどうか」 です。
「この場所が好きだな」
「この人たちと話してみたいな」
そんな純粋な気持ちが、すべての出発点になります。
地域おこし協力隊から二拠点生活を通して、私は地域と小さな関わりを重ねてきました。
それは地域を少しずつ豊かにするだけでなく、私自身の心も満たしてくれる時間でした。
無理をせず、できることからで構いません。
あなたの関わりたいという気持ちが、地域にも、そしてあなた自身にも、新しい豊かさを広げてくれるはずです。

あなたが最近、“ちょっと気になったこと”は何ですか?その小さな気づきこそが、あなたの“関わりしろ”かもしれません。
関連カテゴリー:酒田と横浜、ふたつの暮らしから見えたエシカルライフ